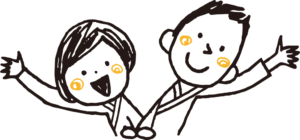自分の身を守り、相手を制する(投げたり取り押さえたりする)武道です。ただし、相手の心身にどれだけ打撃を与えるか、あるいは屈服させるかを目的とするものではありません。むしろ相手を尊重し、相手の心を導き、共に動くことを学びます。
また、私たち人間は本来、大きな力を内に秘めています。合気道を通して体と心の使い方を学び、日常生活の中でもその力を存分に発揮できるようになることが稽古の大きな目的です。
Q&A
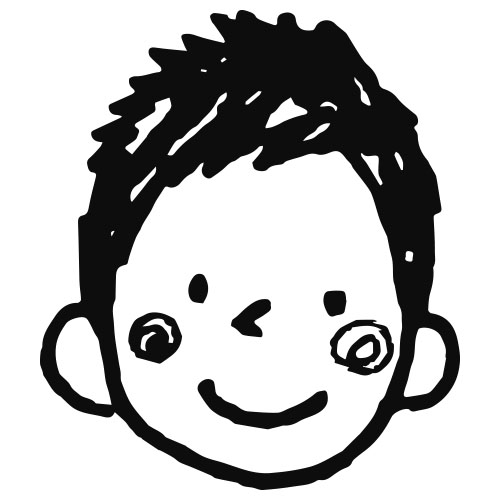
合気道は空手や柔道とどう違いますか

いちばん大きな違いは試合がないところです。想定した状況での技(術)を繰り返し稽古します。
つかむ/打つといった素手の攻撃に対する組み技、短刀(ナイフ)や杖(棒)を使った攻撃に対する武器技、多人数を相手にする技など上達につれて様々な技があり、どのような状況でも動じないで力を発揮すること(不動心)を稽古します。
日々稽古を重ねて自分自身の向上をはかるという点では、どの武道も同じです。

運動をあまりしたことがないのですが

武道やスポーツが未経験でも大丈夫です。合気道はまず姿勢を整えて、リラックスした自然な呼吸とリズムで動きます。礼儀作法や怪我をしない受け身など、初歩から分かりやすく指導を受けられます。稽古はのびのびと楽しい雰囲気です。
継続して稽古すると、知らずしらず体幹が鍛えられて基礎体力もつき、生活に直結した動きのセンスが磨かれます。

氣ってなんですか

「元気」「強気」「気配」「気になる」「気が向く」「気をつける」「気を使う」「気にしない」「気がきく」「気が散る」「気を抜く」…
たくさんの言葉になじみがあるとおり、「気」は昔から日本人にとって身近なものです。稽古では心を静めて広く気が交流する「気が出ている」状態を作り、リラックスして力を発揮できる心身をつくります。
ちなみに常用漢字では「気」と書きますが、エネルギーが四方八方に交流する本来の意味をあらわす旧字体の「氣」があえてよく使われます。
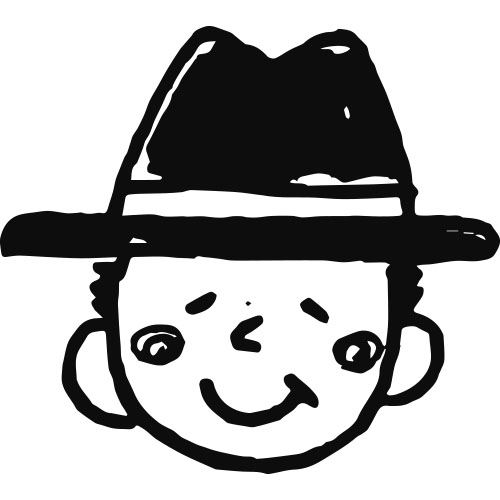
心身統一合氣道という名は宗教っぽいですが

心身統一とは「大自然と一体」である感覚のことで、宗教とは違います。
創始者の藤平光一先生が師事した中村天風先生(ヨガを初めて日本に広めた人物)の心身統一法が由来です。
この哲学は、松下幸之助さん(パナソニック創業者)や稲盛和夫さん(京セラ創業者)らを始め、日本の偉人や著名人に大きな影響を与えました。近年では大谷翔平選手の愛読書として話題になりました。
心身統一(力を最大限に発揮できる体と心の状態)で合気道をするのが、心身統一合氣道です。
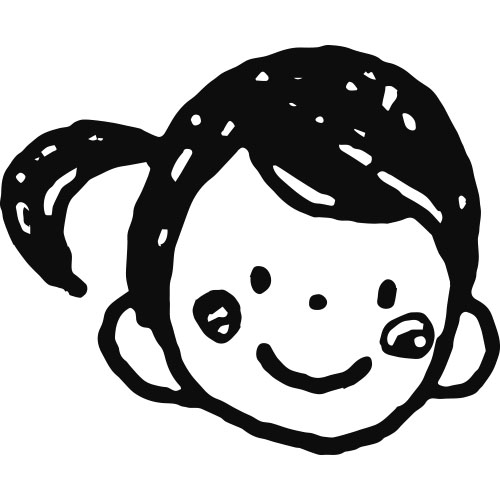
女性にもできますか

「力で相手をねじ伏せる」のではなく「相手を尊重して導く」動きをします。関節を痛めるような危険な技も通常行いませんので、女性にも人気があります。
稽古では余分な力を抜いて、自然体で動くトレーニングをします。日常生活での立ち居ふるまいも自然に美しくなります。

心身統一合氣道はプロのアスリートも習われていると聞きましたが

心身統一合氣道は、筋力に頼らずに体を合理的に動かす方法や、力を発揮するための精神的な修養も稽古に含みます。そのため、道場には現役のアスリートや舞台芸術に携わるパフォーマー、企業の経営者なども珍しくありません。
実際に、野球、バレーボール、サッカー、ラグビー、相撲など、さまざまな競技においてトップレベルで活躍する選手や指導者たちが、パフォーマンスの向上やメンタルトレーニングの一環として学んでいます。
過去には、かつてホームラン王として知られた王貞治さんが、心身統一合氣道の創始者・藤平光一先生の指導を受けたことをきっかけに「一本足打法」を生み出したことは知る人ぞ知る話です。
武道の教えは、身体の使い方や意識のあり方において、非常に大きなヒントとなるのです。
シニア

50代ですが合気道は始められますか

30〜50代で合気道に入門される方はとても多いです。年齢や性別を問わず色々な分野の方が稽古されており、始める目的も様々です。片腕が不自由な方や全盲の方も学ばれています。
書道に「楷書/行書/草書」があるように、合気道の技にも段階があります。体力や習熟度に合わせて、まずはゆっくりのスピードから安全に稽古しますので、安心してご参加ください。
こどもクラス

子どもに習わせると何が身につきますか

健康な身体の土台を作る/身を守る力がつく/楽に大きな力を発揮できる/疲れにくくなる/不動心(動じない心)を養う/感情のコントロール/ストレスを受けにくくなる/集中力がつく/ここぞという場面に強くなる/姿勢が美しくなる/立ち居振る舞いが美しくなる/礼儀作法が身につく/気がきくようになる/隠れた可能性を引き出す
このようなことが期待できます。

けんかに強くなれますか

人を傷つけるための稽古はしませんが、身をまもる力がつき、危険を察知する力も高まります。心身統一合氣道を習って助かったという話はよくあります。
大切なことは、争って相手をやっつけることが本当の強さではないということです。